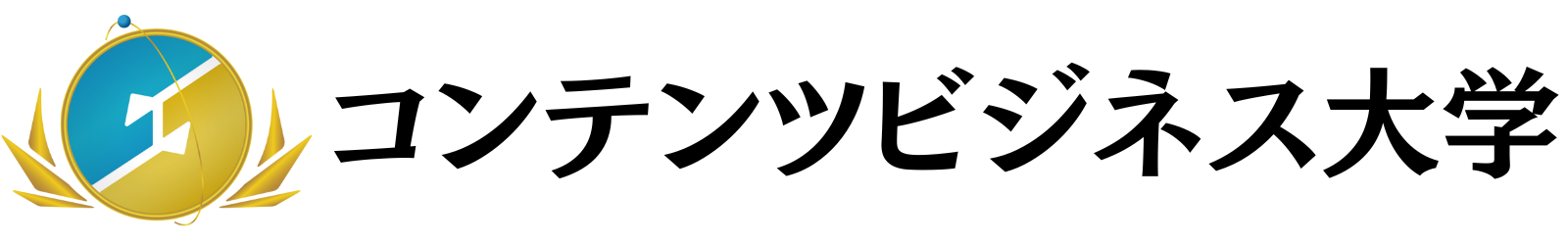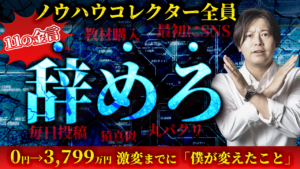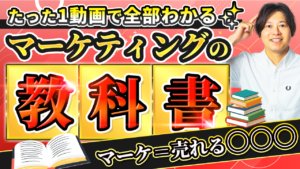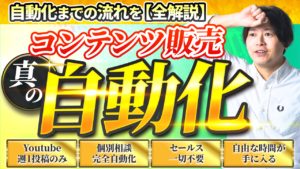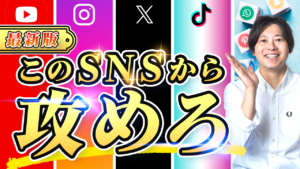「競合になるライバル調査ってどうやればいいの?」
「上手くポジティブをズラして勝てる方法が知りたい…」
後発のコンテンツ販売者がライバル調査できてないと、強みやサポート部分がズラせなかったり、より良いクオリティに上乗せできないので「同じ内容なら実績があるライバルにお願いしよう」とせっかくのチャンスを逃してしまいます。
 ゆーろ
ゆーろライバルリサーチもしないまま、市場に入っても負けるだけで、あなたも同じ商品やサポート内容なら実績がある方にお願いしたいですよね?
そこでこの記事では、お客さんが目の前に現れた時に、たとえあなたが後発からでも「お願いします!」と逆オファーされる商品やコンサルを作るための、ライバルリサーチ方法を教えていきます。
記事の最後にはあなたがライバルリサーチの時間とお金を無駄にせず、ライバル調査を収益に繋げられるようにライバルリサーチでやってはいけない「3つの秘密」も教えていきます。
敵を知らずに勝てる戦略は作れませんので、分からない部分はメモを取りながら読み進めてください。
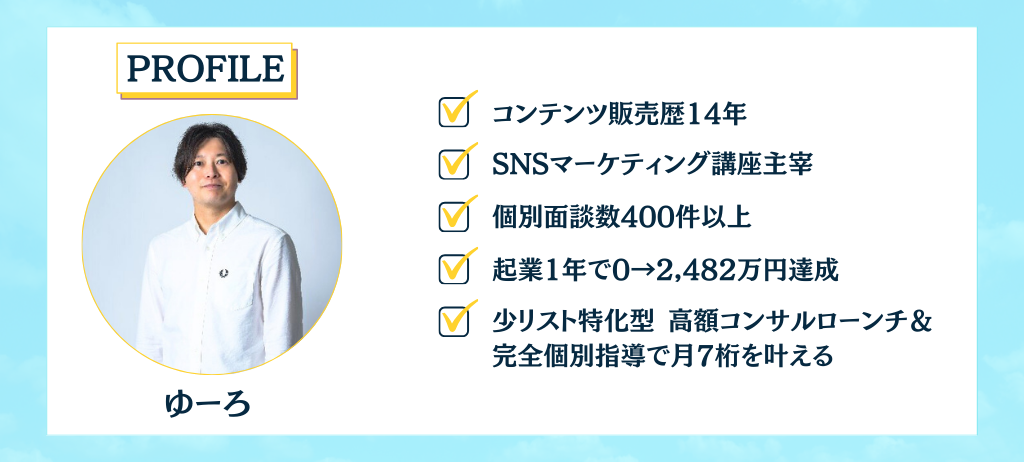
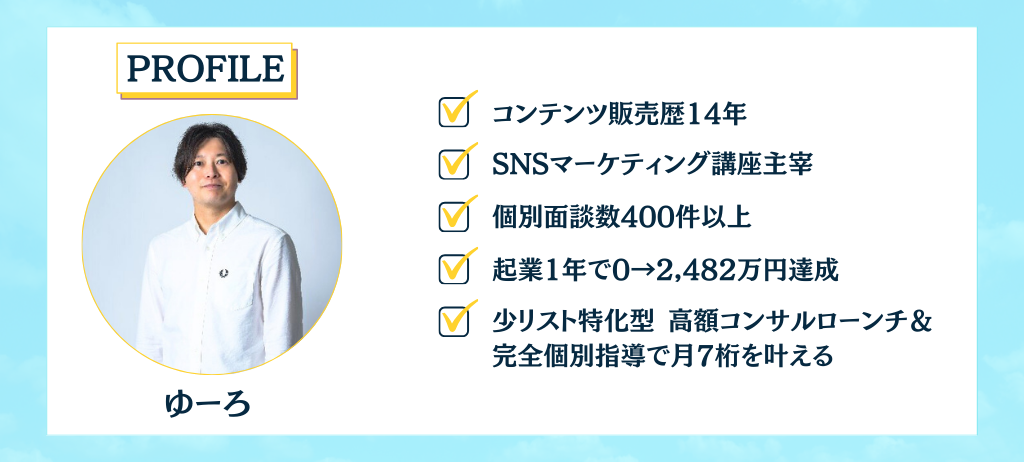
勝てる競合調査5STEPについて
下記のYouTube動画でも詳しく解説しております。
ライバル調査とは?目的を紹介
ビジネス状況とは、例えば売上・従業員数・商品やサービス内容・クライアントの質など色々です。



ライバル調査って本来あらゆる領域について調査するんですけど、今回はコンテンツ販売者に焦点を当てるので、売上・ビジネスモデル・商品内容などを調査すると定義しています。
補足ですがビジネスモデルとは「利益を生み出すための仕組み全般」と覚えてもらえればOKです。
- ライバル情報を正確に理解するため
- ライバル情報を使って勝てる戦略を考えるため
なぜならライバル情報を正確に理解しないと、あなたのビジネスと比較ができないからです。またライバル情報が無いと戦い方も決めることができないんです。



例えばあなたがテニスを始めたい時に、ライバルの特徴を理解しないまま戦略をつくれますか?相手の攻めが強いのか?守りが強いのか、もっというと少し専門的な話になりますが、相手がフォアハンドが得意なのかバックハンドが得意かで戦い方って変わりますよね?
コンテンツビジネスで失敗する人の多くが、ライバル調査の重要性を理解してない、やり方が分からないんで、ライバル情報を知らなすぎるんです。
なぜこういうことが起きるかというと、ライバルなんか関係なくて「良い商品」を出せば売れると勘違いしてるからです。
市場があれば商品は売れる、コンテンツやコンサルのクオリティは大事だ。確かにそうなんですけどあなたが思ってるってことは、それライバルも同じこと考えてますよ?
ハッキリ言って、日本においては良い商品だけでは売れません。なぜなら「商品が良いなんて当たり前」だからです。商品が良いうえに、更にあなたを選ぶ理由があるか、ここが重要なんです。
ライバル調査5STEP
ライバル調査の手順ですが、大きく5つのSTEPで進めていきます。
- 調査対象のライバルを決定する
- 調査&比較項目を決定する
- データ収集
- 比較&分析
- ポジショニング
それぞれ詳しく解説していきます。
調査対象のライバルを決定する
まず初めに調査対象のライバルを決定していきます。



なぜなら調査対象のライバルが決まらないと、誰の情報を調べるべきか決まらないからです。
例えばあなたがハンバーガーショップを開こうと思った時に、マクドナルド・モスバーガー・ロッテリア・ファーストキッチンだと、各社の戦略やビジネス情報って全然違いますよね?
どのライバルを調べるかで全くデータが変わるので、調査対象のライバルを決めるのって1番重要なんです。
ライバルを決める時のポイントはTOPライバルではなく自分と似たレベルのライバルを調べること
あなたは恐らく後発からの参入になるので、TOPライバルを参考にしても当てにならない事も多いからです。
例えばTOPライバルが広告で集客していたり、セミナーを沢山開催していたとします。一方であなたはまだ資金や実績、認知度もないので広告を運用できないし、セミナー集客しても人が集まらなかったり、たった一人に刺さる発信ができないですよね?
このようなことが起きるので、あなたは後発組から参入してSNSで集客したり、個別相談から販売してる様なライバルをベンチーマークすべきなんです。なぜなら似たライバルの戦略を参考にした方が再現性があるからです。
ライバルの決め方
- HPがつくり込まれている
- SNSのフォロワーが数万人以上
- クライアント実績が表示されている
- 顔出しされてる方
- SNSのフォロワーが同じくらい
- 公式LINEの人数が同じくらい
- 集客→個別相談で売上をあげる「弱者の戦略」を理解している
- 自分と好き嫌いや価値観・デザインが似ている
ただし1つ問題があって、それは自分と似たフォロワー数のライバルが果たして売れてるのか判断できないってことです。



SNSや情報発信界隈では、自分の実績にウソをついて発信する詐欺コンサルも多いです。
じゃあライバルを見つけられないじゃんって思ったかもしれませんが、売れている人は発信が有料級・デザインにも最低限、力を入れている。
個別コンサルを受けてみてあなたの問題に的確に答えてくれるか確かめるなどして、チェックしてあなた自身が価値を感じる人であれば売れている可能性も高いので、定性的な判断方法になりますが、このように決めていただければと思います。
調査&比較項目を決定する
STEP②でライバルを調査するときの「調査項目」を決定します。



なぜなら調査項目が決まってないと、ライバルの何について調べるべきかわからないからです。
例えばあなたがサッカーチームに所属していて、監督からライバルチームを調査しといてって言われても「どんな観点で調査すればいいの?」って分からないですよね?
調査すべき項目は戦術か、フォワードに関してか?ディフェンダーについてか?控え選手まで調べるべきかわかりませんよね?
このように調べる内容によって集めるデータが変わってしまうのであらかじめ調査項目を考えてください。
フレームワーク2つ
- 5W2Hでビジネスモデルを確認する調査
- MSPで独自資産を確認する調査
ビジネスモデルとは「利益を上げるための仕組み全般」であり、MSPとはミーセリングポジションといって、ライバルが真似できない実績・経験・キャリア・パーソナリティなど独自資産を指します。
- 誰のどんな悩みを?
- どんな商品やサポートで解決しているか?
- どこで集客・販売・ローンチをするか
- なぜ売れているのか?
- どんな販売導線をしているか
- いくらで販売してるか
ご自身の戦略を考える時に役立つからです。
5W2Hでビジネスモデルを確認する調査
具体的なフレームワークはおさらいしますが5W2H軸で調査していきます。
- Who:どんなペルソナやターゲットの悩みを解決してるか
- What:どんな商品・サポート・特典を調べる
- Where:どこで集客して/どこで販売してるか?
- When:いつ、どのタイミングで販売してるか?
- Why:なぜ売れてるのか?差別化部分は?
- How:どのような販売導線・セールスファネルで販売しているか?
- Howmuch:いくらで販売しているか?
Who:どんなペルソナやターゲットの悩みを解決してるか
法人調査だとさらに細かく調べる必要がありますが、個人発信者の調査であればこれで十分です。
ライバルのターゲットを理解することで誰にサービスを提供すれば売れるか最短で理解することができます。
また、ライバルが解決しているターゲットの悩みを理解することで、既に顕在化したお客の悩みを解決する商品がつくれるのも調査のメリットです。悩みが分かればあとは、その悩みを解決する方法を教えるだけで商品を作ることができます。



僕のクライアントには悩みを50個から100個くらい書き出してもらうワークをやるんですけど、悩みを正確に理解できると商品も簡単に作れるようになります。
ここがチェックポイントですけど「この商品なら売れるに違いない」とプロダクトアウトの考え方で商品を作っても売れないので、お客の顕在化した悩みを解決する商品をつくる「マーケットイン」の考え方で商品は作るべきです。
What:どんな商品・サポート・特典を調べる
「What」ですが、これはライバル調査の中でも商品内容や、サポート、特典を調べます。
例えば最近のコンテンツ販売で言えばChatGPTに関する教材とか広告に関するコンサルが売れているので、ニーズがあると分かりますよね。
また複数のライバルの講座やコンサルに盛り込まれているサポートを導入すればお客さんが満足してくれる確率は上がりますし、ライバルがお客さんを集める時の特典も調べることで効率よくお客を集めることが可能です。
ライバル商品を調べると、ライバルがサポートしきれてないウィークポイントもわかるので、あなたの商品に弱いポイントを補う商品やサポートを付け足せば、見込み客が商品を選びやすくなります。



僕のクライアントも商品サポートがかなり手薄だったんですが、ライバルのサポート内容を見た時にどんなサポートを提供すべきかイメージできて、サポート内容をかなり手厚くできました。
コンテンツビジネスで失敗する人は成功事例を取り入れる量が少なすぎます。既に売れてる人や商品やトレンドはわかってるわけですから、成功事例を自分の戦略に取り入れた方がうまくいくに決まってるので、必ずライバルの商品周りはチェックしてください。
Where:どこで集客して/どこで販売してるか?
3つ目のWhereはライバルはどこで集客してるか?どこで販売してるかです。



例えばライバルがXで集客しているならYoutubeやInstagramに場所を移しても良いですよね?僕の場合はまずXで集客を始めて、発信内容は同じでYoutubeやInstagramに横展開したことで、Xでは出会わない新たなファンを集めることができました。
集客する場所には順番があって、実力があればXから始めるのもOKですが、最初のうちは認知や企画の反応を取るのは難しいので、Instagramで認知を取って実力をつけてからXやYoutubeに参入するのがオススメです。
When:いつ、どのタイミングで販売してるか?
4つ目のWhenはライバルがいつ・どのタイミングで販売してるか確認します。



あなたもXやInstagram企画をする時にライバルと被ったことってありませんか?これライバルがローンチをするタイミングって、新年の「よし頑張ろう!」って思うタイミングだったり、副業マンの予算に余裕があるボーナス月だったり、研究されたタイミングでプロモーションしてるんですね。
真正面から同じタイミングでローンチすると実績者の企画と被ってしまうため、プロモーションのタイミングをズラすためにも「販売時期」の研究は欠かせません。
ライバルがお客さんを集客してから、どのタイミングでセールスしてるか研究すると、近年のセールストレンドも見えてきます。
例えば昔まではメルマガで7日とか1週間とかプロモーションするのが普通だったんですが、近年はお客さんが色々な発信者から情報収集してるので、そもそもメッセージや動画を見てくれないんです。



そこで多くのライバルは公式LINEに登録したらすぐ1本の動画を見てもらってそこでお客さんにファンになってもらったり、商品を欲しいと思ってもらうLiveやウェビナーを行った後に販売するのがメインだったりします。
このように、セールスのタイミングも理解できるようになるので、ライバルのプロモーションや販売のタイミングは押さえてください。
Why:なぜ売れてるのか?差別化部分は?
5つ目がWhyです。これはライバルが「なぜ売れているか?強みは何なのか?」徹底的に調べる作業を指します。
例えば、
- 他にはない圧倒的な差別化ポイントがあるのか?
- 実績が桁違いなのか?
- 商品やサポートが魅力的なのか?HPやセールスページが魅力的なのか?
- お客様の声が多いのか?本人の人柄が良さそうなのか?
徹底的に調べてください。意外とライバルによって売れている理由が違うので、参考にすべき部分が多いです。



例えば僕の場合、人気や認知は勝てないけどコンテンツ販売に関するキャリア・知識は負けてないので個別で1人1人教えることで価値を感じてもらう戦略をとっています。結果的にクライアントに大満足してもらっており、改めてライバルまたここでの注意点はTOPライバルだけ見ずに、あなたと同じレベルで収益化してる人をチェックすることです。
似たライバルで売れている発信者を参考にした方が、商品改良する際に再現性があります。いつまでも結果が出ない人は、努力するけど改善できてません。
つまりライバルが売れていて、あなたが売れていない理由を潰せていないんです。ライバルの強みや、ライバル独自の資産は必ず研究して参考にしたり、ライバルよりクオリティの高いサービスを提供できるように自己研鑽してください。
How:どのような販売導線・セールスファネルで販売しているか?
6つ目Howですが、これは「どのような販売導線」で販売しているかです。
例えばライバルは集客した後に
- 公式LINEとメルマガのどちらで教育してるか?
- 1度オープンチャットに入れて教育してるか?
- 教育後は個別相談に案内しているのか?
- ウェビナーに招待してるのか?
- 参加型の合宿を採用しているのか?
など、商品を売るまでの流れが鮮明に見えてきます。



売れている販売導線を理解すればその導線を採用することで、集客から販売までの仕組みをスムーズに構築できるので、ライバルの公式LINEやメルマガに登録して研究してみてください。
販売導線の研究と同じくらい重要なのが「スクリーニング」の仕方です。
どのお客さんが良いなどはありませんが、例えば上級者向けの商品を販売している人が、初心者の人を集めると「内容が難しい」と置いてけぼりになっちゃいますよね?
そうならないように「初心者の人はご遠慮ください」などどこかのタイミングで絞り込んでいるわけです。



ちなみに僕の場合は普段からあなたのようにYoutube動画を見てくれている人や、僕のLINEに登録して勉強してくれているに教えていきたいと考えているので、少し長めの動画を作って敢えて見てもらうようにもしています。ビジネスリテラシーが高い人に教えるのが結果を出してもらえる近道だと分かっているからですね。
息の長い発信者になるためには「自分の思想とあった、結果を出せるお客さんを集める」事が最重要なので、販売導線と合わせてチェックしてください。
Howmuch:いくらで販売しているか?
7つ目は「Howmuch」です。ライバルの商品価格をチェックしてください。
似たような価格帯にすれば商品は売れやすいですし、より高級ブランディングしたければ、ライバルより高い金額を設定することも可能ですし、着実に実績を作りたいならライバルより安い金額でまずは実績や経験を貯めることも可能です。
松竹梅で商品を販売してる場合、各プランの価格もチェックしてください。



僕が試してみて効果が大きかったのは、売れているライバルのコンサルフィーやコミュニティでコンサル販売してる人の価格を参考にさせてもらって、実績や知名度がないうちはライバルよりも少し安い値段でサービスしたりしました。
お試し価格を設定することで、金銭的なハードルを乗り越えることが出来るので、ぜひあなたも試してみてください。
MSPで独自資産を確認する調査
ライバルのMSPについて調べるのは一言でいうと「ライバルが選ばれる理由」がよく理解できるからです。



例えばライバルが人気なのは、古参でキャリアが長いからか?知識・スキル・経験が豊富だからか?それとも実績があり信頼されるから?それとも発信者の人柄や雰囲気が素敵でファンがついているのか?この当たりが研究で見えてきます。
実際、ライバルの独自資産はあなたが真似できない部分なんですが、ライバルが売れてる要因を取り入れることはできますよね?
実績が必要なら実績を積み重ねるために何をすべきかは考えることができるし、雰囲気で選ばれてるなら「選ばれる雰囲気」を作るにはどうすべきか、ここも考えることは可能です。
ライバルは実績があるから売れているんだと思考停止しないように、考える癖をつけて、良い所を取り入れてください。
- ライバルのHPをみて売上やお客様の声を拾う
- LP・セールスレター、ブログを見てライティング内容について研究する
- TwitterやInstagramやYoutubeなどのSNSの発信を参考にする
- Brainやnoteで販売しているフロントエンドを買ってみる
- ウェビナー・コミュニティ・コンサルを受けて学ばせていただく
- 公式LINEやメルマガに登録して販売導線を研究する
- Facebookページ・Meta広告ライブラリをみながら広告内容をチェックする
この7つの方法でチェックしていけば、100%の情報は見つからないかもしれませんがライバルのビジネス環境を網羅的にチェックできます。
データ収集・比較&分析
STEP④でこれまでの調査データを参考にしながら、あなたの現状と比較分析を行っていきます。
なぜならライバルとあなたの違いを比較分析しないと
- ライバルより選んでもらえる理由を作れない
- より品質の高い商品が作れない
- あなたが売れない理由を修正できないから
からです。ライバルチームの戦術を研究した所で、それを活かしてどんな戦い方をするかまで決めないと全く意味がないですよね?



多くの発信者がライバル調査を活かしきれないのはこのSTEP④の比較分析ができてないからです。
ライバルのデータを元に、あなたがライバルに勝っている部分はどこなのか?それはなぜか?一方でライバルに負けている部分はどこか?それはなぜか?そしてライバルと比較したうえで、どのようにあなたのブランディングや商品を改善できるのかを分析していきます。
僕のクライアントが後発からでも着実に結果を出せるのは、分析シートを使いながら僕とクライアントで徹底的に比較・分析するからです。
ライバル調査の中でも、最も重要なSTEPなので、ライバル情報を集めた時と同じくらい、ご自身で比較する時間と、比較した結果を踏まえてどのような戦略を練るのか?施策を打つのか考える時間をとってください。
ポジショニング
ポジショニングとは、あなたがお客さんに伝えたいターゲットに対して、どんな訴求をして集めるのか「ポジション」を決めることです。
例えばラーメン屋の例で話すと、まず30代の男性をターゲットに設定した場合、あなたのポジションを決める軸を決めていきます。ラーメンの要素を分解していくと、
- スープ(豚骨なのか醤油なのか)
- 麺(ストレートかちぢれ麵か)
- 具(チャーシュー・メンマ・もやしなど)
- 外観
- 内装
- 器
- 価格
など分解できますよね?



それぞれの要素において、どれを選んでいくのか?これがポジショニングに当たります。
同じ様なポジションって少ないし、微妙にポジションが違うと思いませんか?お客さんからは分かりにくいかもしれませんが、あなたは他のお店と何が違うのか、だから選んでもらえるんだといったポジションを理解しておかないといけません。
ポジショニングが明確になってないと、中途半端な意見の発信になったり、たった1人に刺さる発信ができないので必ずポジショニングしたうえで発信を始めてください。
ライバル調査でやってはいけない3つのこと
- ライバル調査しただけで終わる
- ライバル調査で自信を失う
- 実績がないままライバルに勝とうとする
実はライバル調査でやってはいけないことがあるので、クライアントとこの動画を見てる人以外には教えてない「ライバル調査でやってはいけない3つのこと」を紹介していきます。
ライバル調査しただけで終わる
1つ目が何度もお伝えしたように「ライバル調査しただけで終わる」これがもっとも時間を無駄にする間違いです。



実は上場企業でも個人でもこれが多いんですが、ライバルの調査をして満足する人が多く、その内容をどう自分に活かすのか?ライバルの情報が分かったから、どんな戦略を練るのか?この部分を考えるまで至ってないケースです。
これでは時間を無駄にするだけで、何の結果も得られないので「ライバル調査と商品改良やポジション決定はセット」と覚えといてください。
ライバル調査で自信を失う
2つ目の間違いが「ライバル調査で自信を失う」ことです。
ライバル調査をしてると自分より実績やキャリアのライバルばっかりなんですよ。そんなの当たり前なのに「自分は実績がないとか、ライバルには勝てない」と思ってしまうと本末転倒です。
問題はそんなところじゃなくて、ライバルが強くて、今の自分のスキル・実績であれば、どうやってお客さんを集めて販売していくか?この戦略を考えることに意味があるんですよね?
繰り返しますが後発組なんて、ライバルより実績がないことがほとんどなので、一切気にせず「自分を必要としてくれるたった1人のお客さんを探す気持ち」でライバル調査に取り組んでください。
実績がないままライバルに勝とうとする
3つ目の間違いが、実績がないままライバルに勝とうとすることです。
今勝てないなら「勝てるためのスキルや、喜んでもらった感想を集めろ」ってことです。先ほどもお伝えした通り、ライバルの方が強いなんて当たり前です。



あなたは実績もスキルもまだないなら「ライバルに勝てそうな部分」を調べて、その部分のスキルや実績を作りまくればいいんです。
僕自身、コンテンツ販売のライバルが多くて上手くいかなかったときに、自分のキャリアや実績を振り返りました。他のライバルに無い所が「100万以上の高額商品」を販売してきたことだったので、そのメソッドを体系化して伝えていったところ、名指しで選ばれるようになったし、自分が選ばれるように高額商品を売るためのスキルを学んだり実践してきたんです。
どれだけライバル調査をしても実力も実績もないままでは、選んでもらえないので、ライバル調査と合わせてライバルに勝てるスキル開発や実績作りに励んでください。
まとめ
今回はライバル調査のやり方とフレームワークを完全解説といったテーマでお伝えしました。
上場企業でさえ、良い商品を作ったり、ライバルに勝つ戦略を練るために、取りくむのがライバル調査と言われる程のライバル調査の威力は半端ないです。
ライバル情報が明確になり、効率よく販売導線を作ることもできますし、ポジション、いわゆるあなたが選ばれる理由もつくれるようになるので、この記事や動画を見ながら実践していただければと思います。